建築物と省エネルギー性能のこれまでとこれから
省エネ性能の評価指標
建築物の省エネルギー性能は、大きく分けて「外皮性能」と「一次エネルギー消費量」の2つの観点から評価されます。
初めて学んだ省エネの概念
この2つの概念について初めて学習したのは、平成25年に受講していた一級建築士講座、学科Ⅱ「環境・設備」のテキストの中でした。
学科Ⅱは私にとって苦手科目であり、試験ではなんとかギリギリでクリアした記憶があります。
平成28年度 講習の様子
その後、省エネ基準の改正に伴って、平成28年度に多くの講習会が開催されました。以下はその修了証です。
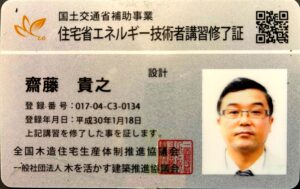
配布されたテキストは、設計・基本・施工の3冊に製本された本格的なものでした。
これは「平成29年度 国土交通省補助事業『住宅省エネルギー技術講習』」で、仙台で開催され、対面でのライブ講義形式。まだコロナのずっと前のことです。
オンライン講習時代へ
やがて新型コロナウイルスの蔓延により、省エネ講習もオンラインへと移行。
その際に届いたのが「改正建築物省エネ法オンライン講座テキスト(令和2年7月時点版)」。
これは“緊急措置”として編成されたものでした。
令和7年の法改正
令和7年4月1日、省エネ法改正が全面施行され、すべての建築物に省エネ基準への適合義務が課せられました。
これまでの流れは以下の通りです:
- 中・大規模非住宅建築物から適合義務スタート
- 適合義務→届出義務→説明義務と段階的に拡大
- 現在では住宅・非住宅、中・小規模すべてが対象
便利な資料ライブラリー
現在では、国土交通省の「資料ライブラリー」に、オンライン講座・Q&A・各種ガイドブックが豊富に揃っています。
わかりやすい解説から専門的な計算例まであり、省エネ法や建築基準法の調査・学習に最適です。ブックマーク必須のサイトです。
まとめ:DXとBIMの時代へ
新型コロナが収束した現在も、ハラリ氏が語ったとおり、パンデミック時代の社会構造や技術は今も定着しています。
書類は電子化され、押印文化も後退、ペーパーレス化が進行。建築確認も電子申請が推奨されるようになりました。
そして最近届いたのは「国土交通省によるBIMの取組のご案内」。2026年春より始まるこの制度には、「新しい建築確認」「補助金案内」などの記載がありました。
法改正に追いつくのもやっとという中で、また新制度…。
でもBIMはすでに大規模建築等では活用されており、「ドラフター→CAD→BIM」と進化する流れの一環なのだと、広告だけでなく現実として実感しています。
