真太陽時とは?均時差と経度差で求める真北測定|日影規制と建築実務
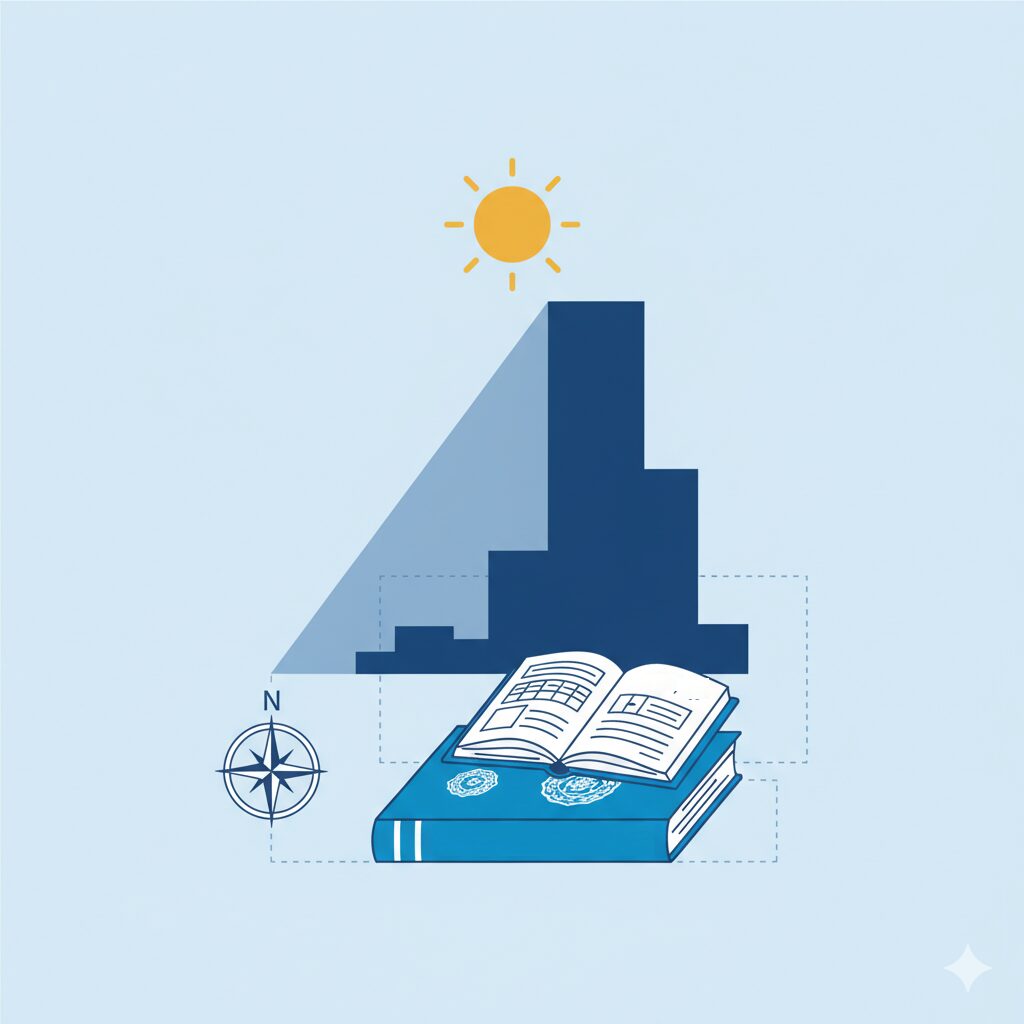
真太陽時って何?均時差?
「理科年表」と「東京都建築安全条例とその解説」で学ぶ日影規制と真北の求め方
建築確認で日影規制のかからない案件だと、「平均地盤面」や「真北方向」の扱いがつい曖昧になりがちです。しかし実際には、真北の誤差ひとつで建築基準法違反とされ、建物の一部を削る是正命令に発展した事例もあります。
ここでは、**「東京都建築安全条例とその解説」**を手掛かりに、日影規制における「真太陽時」「均時差」「経度差」と真北の測定について整理してみます。
日影規制と真北
建築基準法 第56条の2(中高層建築物の高さ制限)では、
測定時間は 「冬至日の真太陽時 午前8時〜午後4時」(道の区域内は午前9時〜午後3時) と規定されています。
ここでいう「真太陽時」とは、平均的な時刻(中央標準時)ではなく、太陽そのものの動きに基づく“視太陽時” のことです。
真太陽時とは?
-
1日=南中から次の南中まで
太陽が真南に来る瞬間(南中時)を基準とし、そこから次の南中までを1日とします。 -
中央標準時とはズレる
日本の標準時は「東経135°(明石市)」を基準とした平均太陽時です。
しかし実際の太陽の動きは季節により変動するため、平均時刻とずれが生じます。
均時差とは?
太陽の動きと平均時刻の差を「均時差」と呼びます。
式で表すと:
e=t-tm
-
e:均時差
-
t:真太陽時
-
tm:平均太陽時
(+の場合は12時からn分早く南中する、-の場合は遅くという意味になる。)
「理科年表」や国立天文台のサイトで均時差は確認できます。暦象年表令和7年2025
経度による時刻差
さらに、測定地点が明石市(135°E)からどれだけ東西に離れているかで時刻差が生じます。
tm-ts=(L-135°)/15°x60分
-
ts:中央標準時
-
L:測定点の経度
つまり、均時差と経度差を合計したものが、その地点の真太陽時と中央標準時のズレになります。
最終的な関係式は:
t=ts+e+(L-135°)/15°x60分
真北の測定
現地で磁石やスマホアプリを使う方法もありますが、簡便かつ確実なのは 太陽による方法 です。
-
南中時(真太陽時12時)に下げ振りの影を利用する。
-
影の方向が真北を示す。
重要なのは、その日の南中時が中央標準時で何時に相当するかを事前に計算しておくこと。
式で表すと:
ts=t-e-(L-135°)/15°x60分
ここで t = 12時 とすれば、現地での南中時(中央標準時での時刻)がわかります。
日影図の作成
「東京都建築安全条例とその解説」には、冬至日の太陽高度・太陽方位角・日影の倍率(x成分・y成分)が一覧表で示されています。
-
これを使えば、配置図に時間日影図を手書きで起こすことも可能。
-
n時間日影線も、8時と10時、9時と11時という風に、日影図の交点を結ぶことで作成できる。
*日影倍率は真太陽時の正午12時の太陽方位角を0°として8:00=16:00、8:30=15:30、9:00=15:00、というふうに、左右対称になっていることが分かります。太陽方位角も12:00を0°として左右対称、太陽高度は南中時の12:00が最も高く、8:00と16:00が最も低くこれも左右対称です。
*日影倍率は建築物の高さを1とした場合の影の長さの倍率です。
まとめ
-
真太陽時:太陽の実際の動きに基づく時刻。
-
均時差:平均時刻との季節的なズレ。
-
経度差:明石基準からの地理的なズレ。
-
これらを組み合わせて南中時を求め、日影から真北を測定する。
日影規制は単なる図面作成作業ではなく、天文学的な基準を押さえてこそ正確さが担保されます。
「理科年表」と「東京都建築安全条例とその解説」を横に置きながら、現場での実測と設計を結びつけていくことが肝要です。